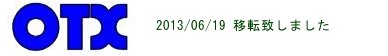
当時の手書きの資料で、
再現期間30年の風圧力に対しての記述がある。
建設地における実際の風速の
強さ、頻度(再現期間)を考慮して設定する。
PCーテンウォールの持つ外壁としての諸性能を
計画的耐用期間
仮定した使用条件及び経済的要求
作用荷重の頻度、裁荷期間
荷重の形式(静的、動的)
他の部位(目地、サッシ)との性能上の釣合い
材料及び解析上、製作上の安全率
特にパネルの配筋設計においてこの程度の性能設定に
しても適切な配筋法を採用することにより、
在来の設計法による配筋量に比較しても過大な設計
とならないことを検討した上で設定された。
過大な設計とならないと記されているが、私にとっては過大な設計に思えた。
なお、この文章は25年以上前のものである事も考慮して頂きたい。
再現期間nn年の風圧力の計算式の概要は以下のような物である(式は省略)
1)基準風速の設定(東京では27.4m・/s 地上10m、10分間平均)
2)再現期間nn年の補正
3)鉛直方向の風速の補正
4)突風率の設定
5)最大瞬間風速の算出
6)基準風圧力の算出
7)地域係数の補正
その後、日本建築学会にて風荷重設計指針が発表され、
現在ではその式を使用しているが、それ以前に比べると風圧力が過大となってしまった。
配筋計算式は以下の2通りの設定があった。
(現在でも使用中。式は省略)
1)
ワイヤーメッシュによる2方向配筋の場合
アメリカコンクリート協会(ACI)の算定式を使用する。
2)
普通の1方向配筋の場合
コンクリート構造物設計施工国際指針(CEB−FIP)の算定式を使用する。
最大荷重で100回程度の繰り返し荷重を受けた場合ある。
最大許容ひび割れ幅は次のように設定されていた。(以下、記述の写し)
諸外国に見られる最大許容ひび割れ幅の推奨値
ACI Committee 224
露出条件
最大許容ひび割れ幅(mm)
乾燥空気または保護膜
0.40
湿気、湿った空気、土壌
0.30
凍結防止剤
0.18
海水及び海水噴霧、湿潤
0.15
水を保持する構造物
0.10
CEB−FIP
最大許容ひび割れ幅(mm)
屋外では0.15〜0.25mm程度が定説のようであるが、
永久荷重と長期に作用する変動荷重
永久荷重と変動荷重の不利な組み合わせ
有害な露出条件下の部材
0.1
0.2
保護されていない部材
0.2
0.3
保護されている部材
0.3
美観上のチェック
PCーテンウォールの場合、パネルの板厚が比較的薄くかつ2次部材として
外側表面全体が常に屋外に露出され、特に風圧力によって繰り返し荷重を受けるため、
ここでは次に示す値とした。
荷重時の最大許容ひび割れ幅を0.2mm以下。
荷重除去後の残留ひび割れ幅は荷重時の50%とし、0.1mm以下とする。
その後何年か経過し‥1980年頃から私は鹿島建設の仕事を多くするようになった。
最初の頃は大変である。
『何故30年なのか』の説明が必要であった。
他のゼネコンではそのような設定は無い訳であるから‥なおさらで難しい。
説明する方も全勢力を費やし‥説明を受ける方も消耗し‥
その説明が終わった頃には計算書の中身はどうでもよくなってしまうのである。
『後は見ておくから‥』で終わり。
後で私が計算間違いに気が付いても勝手に直して‥おしまい。
だいたいがこんな感じだったような気がする。
しかしやがて、PC業界もこの考え方に追従するようになって来た。
性能維持は再現期間30年の風圧力である。
地震力も同じ0.5Gであった。
但し彼らは独自の計算式を設定したのである。
当然の事ながら、技術レベルの違いから完璧と言えるものではなかった。
この計算式を使うと、鹿島建設の式よりも鉄筋量が少なくて済むのである。
しかし、どこか矛盾があったのに違いない。
その後、PC業界は今までの計算式をいきなり撤回し、
違う計算式を設定したのである。
やはりこの計算式も鹿島建設の式よりも鉄筋量が少なくて済むのである。
PRC式とか言っている計算式である。
これにも疑問を感じる部分がある。
説明を求めたのであるが未だに誰も説明をしてくれない。
しかし相手が鹿島建設でない場合はその式で行っているようである。