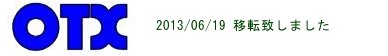
なんと言っても、鹿島建設のPCcw標準仕様の登場である。
昭和48年(1973年)の発足のPCcw標準化研究会によって作成されたものであり、
その研究会は昭和51年に終了しているところから、
それの正式登場を昭和51年と考えていいだろう。
私自身が初めてそれを見たのは、昭和50年であった。
その特徴を大まかにまとめてみる。
1.
最大荷重に対する計算方式は同じ。
但しその荷重に対して断面設計は行わない。
つまり、その荷重で所用断面係数を算出しないということ。
2.
最大荷重とは別にPCcwの性能維持のための荷重を設定した。
風荷重 再現期間30年の風圧
地震荷重 0.5G
3.
その性能維持荷重に対しPC版に生じるひび割れ幅を
許容値以下となるように配筋量の算出を行う。
これは諸外国の例から引用していた。
計算式 ACI式およびCBE-FIP式がベース
許容ひび割れ幅 荷重時0.2ミリ 荷重除去時0.1ミリ
4.
社内にていろいろなモデルによるFEM解析を行い、
それをもとにPC版のモーメント算出用の資料を用意した。
盲パネル チモシェンコの図表を用意
窓パネル 回帰式の設定
5.
標準化ファスナーを設定した。
それは、従来のコンクリートのアゴを否定するものであった。
最大荷重時においては、ファスナーの変形、
またはルーズホールの中ですべることにより、力の解放をするものだ。
PC業界の識者に驚異的な大発明といわせるほどのものである。
6.
リブ版を否定し、積極的にフラットパネルの採用を推奨していた。
最小厚みは130mmと設定。これは、鉄筋の被り圧から決まる。
7.
全社的なプロジェクトであり、蒼々たるメンバーが参加していた。
マニュアルも収まりなどの記載もしっかり完備され充実していた。
このように列記だけでは迫力に欠けるが、実に衝撃的なことだったのである。
まず、再現期間30年。最初の頃は『30年だけ持てばよいの?』
などと陰で文句を言っていたものだった。
次にクラックの許容値。これも『クラックが入ってもいいんだよ』などと、
やはり陰で文句を言っていたものだったのである。
しかし、この基準には十分な説得力があり、
次第に定着していったのであった。
それもゼネコンの壁を超えて定着したのであるから、素晴らしいことである。
ただ、再現期間30年の是非が時々問題になったことは事実である。
要求によっては、再現期間50年で計算することも合った。
おそらく昭和60年頃には完全に一般化していたと思う。
その頃、私は某ゼネコン系のPCメーカーの設計部に在籍していたのであるが、
この鹿島建設の社内基準には驚かされたものである。
ファスナーにやたらお金がかかる‥鉄筋量がムチャクチャ多い‥等‥。
それで対抗策として見積もりの時に鹿島単価とやらを設定したのであった。
技術的にも対応するのが大変だ‥計算式はやたらと面倒である。
思えば当時は電卓など会社になかった。売ってはいるが、かなり高価である。
紙と鉛筆とソロバンで計算をする訳であるから、
気が遠くなるような作業をしなければならない‥。で‥その時どうしたかと言うと‥
上司に言って担当を外してもらった訳である。
幸いに他のゼネコン系のPCメーカーだったため、
それ以上の被害には逢わなくて済んだ。
今から27年前の事であるから未だプロジェクトの最中だったのだろう。
そう考えないと‥年代が合わない。
その時に決められた事の中で、配筋量によるひび割れ制御という項目がポイントとなる。
再現期間30年の風圧力を用い配筋量の計算を行うと言う考え方が示された訳であった。
当時私としては馴染めなかった。
『あっそう。30年しかもたなくても良いんだ‥』
等と言った記憶もある。
しかしその内容は理にかなった物であり、
実際にPCーテンウォールの性能アップになった事は確かである。
それ以前のPCはクラックが入ったり‥と言う事もあったが
(公表はされていない)
それ以来そのようなトラブルは皆無となった。
ただ、それ以前がひど過ぎただけかも知れない。