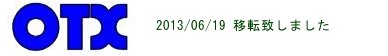
これは、各PCメーカーによってかなり異なっていたと思う。
だから当時すべてがこれから述べる様なことではなかったのであろうが、
とりあえず私がいた会社での話とする。
また会社による違いのみでなく、各個人による違いもあったはずである。
各個人の差としては(言い方が悪いが)ゴミ見みたいな現場ばかり担当していた人と、
そうでない人の差も含まれている。
昔は、とにかく簡単なファスナーだった、というか小型であった。
もっとも、PCパネルのサイズが現在のそれと比べかなり小型であり、
重量も軽く、更に言えば地震力の扱いの違いによるところも、影響が大であった。
パネルの自重はPC版のコンクリートのアゴで、躯体に腰掛ける。
というのもレベルの調整はベースモルタルを敷いてその上に載せる、といったものである。
最も実際はそのベースモルタルのレベルを低めにしてライナーによるレベル調整を行っていたのであるが、
図面上ではベースモルタルのみであった。
それもいづれ、図面上にて3mm程度のライナーを表現するようになったのであるが、
調整代が3mmというのはすごい。
ボルトはたいていM16であった。
PC版には長さ100mm程度のインサートを埋め込み、
躯体側にはM16のアンカーボルトを埋め込む、
といった物である。
その当時RC、SCR,造りが多かったのである。
ファスナーの金物は、L130-12程度が主流であり、
よくもまあ、施工誤差を逃げることが出来たものだ。
当時も一応、層間変位に対する意識はあったようである。
昭和47年に作成されたマニュアルを見ると、
すべり材はテフロン、ボルトは締め込んでから半回転戻すとなっている。
しかし私自身に、その意識があったかどうかは良く覚えていないのだ。
また、当時のルーズホールは本当に小さかったことを今でも覚えている。
M16のボルトに対して22×36程度のルーヅホールだったと思う。
つまり、施工誤差ゼロでスライド量10mmといったものだ。
然し、施工誤差もそのルーズホールで吸収する形になっていたため、
本当に機能しているかどうかは疑問である。
また、当然そのサイズの穴で施工誤差を吸収できるはずも無く、
実際はほとんどの場合、ルーズホールをガスでふかして穴を大きくしていたのである。
そのとき工事担当者に層間変位という意識があったかどうかは定かではない。
私だったら、最初から大きくすれば良いのに、
と今では思うが、私自身その当時は全く考えなかったのであった。
なお、すべり材のテフロンであるが、その会社の他の人を含め、
使った記憶は数えるほどしかなかったような気がする。
また、当時は、躯体の精度も良くないことが多い様であった。
PC版を持っていったら梁にあたる、
そこで鉄筋が出てきた、とかスラブをはつったら取り付け用の
アンカーボルトが取れそうになった、とかいう話を聞いたことがある。
その後、それをどうしたかは聞いていない。
ひとつだけ聞いた工事がある。
大阪の某ビルであるが、はつったらアンカーボルトの被りが50mm程度になってしまった。
しかし、そのまま取り付けた、ということである。
ここで名誉のために付け加えるが、全ての工事がそうだった訳ではない。
これは、昭和46年頃だったと思うが、大手設計会社の現場があった。
それはS造の梁柱タイプのものだったと思う。
早速図面を書き打合せにいったのであるが、いきなり
『こんな小さなルーズホールでは駄目、30×50にしなさい』
と指示があり、図面を書き直したのであった。
ルーズホールを大きくすると座金も大きくなるし、
当然ファスナーはL-150になる。
工事課長に『何で大きな金物を使うんだ』と、文句を言われた記憶もある。
当然金物代はアップ、その後、その会社用の単価が密やかに設定されたような気もするが、
はっきり覚えていない。そういえば昭和50年頃、某地所単価も合ったようななかったような。
しかし、このように書くと、昔はこの程度のことしか出来なかったように聞こえるが、そうではなかった。
やはり、大きなプロジェクトはちゃんと検討されているはずであるし、
それ以外のものも全てこんな感じではなかったはずである。
しかし、私に残っている記憶はここで述べているようなことなのだ。
その原因はおそらく大きなプロジェクトを担当させてもらえず、
ゴミみたいな仕事が多かった、ということだったと思う。
逆にいえば大きな工事はしっかり計画され、現在でもその資料は残っているが、
それ以外の工事の資料はほとんど無いのである。
そのためにも、ここで当時の良くなかったことを書くことは必要なのであろう。
昭和50年頃になると、すべてのケースにおいてルーズホールは
施工誤差を吸収でき、なおかつ所用の性能が確保できたのものになってきたと思う。
その頃になると、層間変位時におけるPC版の挙動図なども描かれるようになっており、
全体的にPCcwの性能に関しての意識が高まってきていたのだ。
もっとも、自然にそうなったのではない。
その要因として考えられることはそれまでに行われてきた実大実験、
特に面内変位性能実験によるところが、大であったのだ。
実験に立会い、実際にPC版が動いているのを見たことが
より理解を深めることに大いに役立っていたのだ。
そういえば、面白い実験装置があった。
某ゼネコンの技術研究所で見たのであるが
『衝撃式振動台』
というやつだ。
原理は簡単で、吊り下げ式の振動台に、振り子式の重り
(はっきり覚えていないが、30トンくらいの重量の鉄の塊)
をぶつけて衝撃力を与える。というものだ
。今になって考えると、かなり乱暴な方法であり、データの整理なども難しそうだが、
その時は本当に驚いたものである。
面内変位追従性実験
今はまず失敗することはない、しかし最初の頃は失敗したこともあったようで、
たとえば長い全ねじボルトを使い、その曲げ弾性で変位を吸収しようとしたところ、
実験のときボルトが切れてしまったとか。
昭和45年頃見学したのであるが、某ビルの静的変形追従実験で
板ばねのストロークが不足しており、
実験中PC版のアンカー部にクラックが入り、
パカパカになってしまったというようなこともあったのである。
おそらく、これらは内緒になっているのであろう。
ここまで書いていて思い出したことがある。
昭和48年頃だったと思う。スウェイ方式で行う超高層ビルであった。
現在ではコーナーの目地幅を計算して、当然その幅を広くする、
ということになるが、そのときはそうしなかったのである。どうしたのか?
『その板のばねのアイデァを盗み、
コーナーPCが隣のスウェイ版に押されたら反対側の面に回転して逃げる』
というものであった。
45度方向の変位を考えていなかったのか、目地幅の中で逃げられると思ったのかは
覚えていないが、本人も今まで忘れていたのであるが、その当時そんなことも考えていたのであった。
その当時、層間変位追従方式は3種類あった。
スウェイ方式 →初期から採用されていた
ロッキング方式 →昭和45年頃から
ハーフロッキング方式 →昭和47年頃から?
(昭和47年のマニュアルには混合方式と記されている)
ところで、このスウェイ方式という名前はいつごろついたのであろう?
昔はスライド方式と呼ばれていたのである。
私の記憶では、昭和50年代の中ごろまではスライド方式と
呼ばれていたような気がするが…
PCCAの技術部会がどこかで、スウェイ方式に決めたのであろうか?