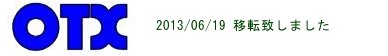
昔は、なんと言ってもリブ版が多かった。
軽量化が命のごとく肉を抜き、スラブ部分の薄いリブ版を作っていたのだ。
その薄い部分の厚みは、私の頃で80ミリ程度が主流だったが、
それ以前の図面で60ミリ程度のパネルを見た記憶がある。
配筋はたいていリブの主筋がD-13、
スラブ部の配筋が6ミリ―100@
(もしかしたら150@だったかもしれない)
といった感じである。
当時、そのスラブ部分の面積を1.5から2㎡以下にする、
というのがルールとなっていた。これは収縮クラックを防止するためであった。
そのようなリブ版が一体いつの頃からなくなったので
あったかはっきり覚えていないが、
おそらく昭和40年代の後半に終わっていたであろう。
私自身では昭和48年頃、リブ版の図面を描いたのが最後だったような、気がする。
そのとき、何故フラットパネルにせずにリブ版で図面を描いたのか?
その理由は定かではないが、おそらく何も考えずに、
「いつもこうだから」
と習慣的に図面を描いただけなのであろう。
当時すでに収縮クラックのことは問題になっていたはずだと思うが、
では具体的にどうすれば良いか?このことについて具体的に会社的な指示は無かったと思う。
まして、自分自身にその解決策を考える能力も無かったし、
そんな気も無かったのである。
その頃、やたらと忙しくて目先の仕事を消化するだけで精一杯、というような状態だったと思う。
ところで、技術的な問題に対しての社内チェック機構はどうなっていたのであろう。
私がいた会社に限って言うとそのようなものは無かったような気がする。
最も設計スタッフの定着率の悪さから、私よりキャリアのある人が設計にいなかったことと、
そのときの設計課長とウマが会わなかったことも、
社内にチェック機構が無かったと思わせる原因かもしれない。
しかし、いづれにせよ個人プレーで仕事をしていく人が多かったことは確かである。
話が横道にそれたが、当時リブ版が多く、またリブ版の収縮クラックも問題にされていたのであるが、
上記のようなことがその問題の解決を遅らせた要因の一つであったとも考えられるのではないか。
これはいつ頃か忘れたが、初めてフラットパネルに出会ったとき、
配筋図を書くときにとても困った。
配筋の仕方がわからないのである。
結局リブ上に鉄筋を打ち込み、上下からスラブ用の6ミリ金をかぶせたものを作ることにした。
断熱材打ち込みのサンドイッチパネルの配筋と同じ物である。
自分自身、はっきり意識をもったフラット版、それは昭和50年だった。
パネルサイズはたぶんW2400、H4300だったと思う。
構造上の問題でパネルを軽くしたいという要求があった。
そこで出来る限り計算し、その結論を厚み120ミリのフラットパネルで可と出した。
そして鉄筋のかぶり圧は25ミリとしたのである。
これは建築学便覧をたよりに、中性化速度の計算をした結果であった。
もしかしたら係数を間違えたのかもしれないが、
その結果、何百年という耐用年数が出たのである。
このとき、初めて水セメント比の重要性を知ったのである。
中性化の速度がそれによっても全然違うのである。
このプロジェクトには、他のPCメーカーも参加していた。
その会社はかわいそうなことに最終的には仕事を取れなかったのであるが、
現場事務所に常駐して図面を書いていたのである。
その担当者曰く
『そんなぺらぺらなパネルは作れない。ストック中でグニャグニャに反ってしまう』
そう言われてみると確かにそうである。
しかし、ここで私の「思い込み個人プレー精神」が頭を持ち上げたのである
「絶対作れる」…ということで反対意見を出したその会社で試作したのであった。
その結果は『良かった、恥を書かずに済んだ』ということである。
ついでにファスナーにもクレームがついた.
『微調整機構がないと駄目』
それでないと職人が仕事をしないということである。
それは了解して図面を書き直したのである。
重さが500kgの二階建てのファスナーというやつだ。
つくづく『会社で違うんだなあ』と思ったのであった。
昔はパネルの幅も現在ほど大きくは無かった。
それは意匠上のことが問題と考えられるが、
その当時の重機の能力の問題とか、輸送上の問題などの要因もあったと考えて得てよいと思う。
PC版の幅をトラックのサイズから、
必死になって2400ミリ以下にした記憶もある。
昔は輸送上の規制が厳しかったようにも思う。
昭和47年だったと思うが、パネル幅が3000mmを越えるものを
東京から大阪まで先導車をつけて低床トレーラーで運んだような記憶もある。
それがいつから現在のような大型パネルになってきたのであろうか?
その時期を特定することは難しいが、
昭和51年の鹿島建設のPC標準化では現在の大型サイズは考えていない。
ということは大型化はそれ以降なのであろう。
おそらく昭和55年頃からではないだろうか?
輸送認可のことは良くわからないが、とにかくPC版が大きくなってきた。
いまやパネル幅3200mmはあたりまえで、
時には3600mm近いパネルも作られている。
その背景にはPCメーカーの技術力アップによりそれが可能となってきた、
と考えても良いのではないか?
そのきっかけは、設計者の要求『出来るだろうか?』から始まっていると考えられる。
おそらく最初はPCメーカーは頭を抱えたのであろう。
しかし試行錯誤を重ねながらも要求どおりに建物は完成すると自信がついて来る。
「よし、次も…。」というようなことで、それが前例となり次々に大型パネルが計画されたのだ。
ただ気になるのは、トラックの荷台からはみ出して、
PCパネルを運んでいることである。
現在の交通事情を考えると、これは社会情勢的にまずいのではないだろうか。
だからいつまでも『土建屋は…』といわれるのである。
しかし、他に輸送手段がないのであるから仕方ない。
そろそろ、特殊BODYを持った専用トラックが出てきてもおかしくはないが。
それとは違う方向の大型化もあった。スパンドレルPCの大型化である。
これは、意匠上のことも関係しているのであるが、
それよりも大型化によるPCcwのコストダウンの方が比重は大であったと考えても良いであろう。
いまや6400mmは当たり前、
時には8000mmを越すスパンドレルPC版も普通に作られるようになってきた。
これも同様に、昭和55年頃からだと思うが、
最初の頃はやはり『おそるおそる』といった感じもあった。
昔も時々大きなPC版はあったのだが、
昔は多少パネルが反っていても何とか勘弁してもらえる雰囲気も合ったが
(これは思い違いかもしれないが)
この頃はそのようなことが許される時代ではなかったのだ。
だから、最初の頃はかなり気を使って、それに望んだのである。
まず、断面を決める。
これは所要強度を確保しながら、出来るだけ軽くなるような断面形状を選ぶのであるが、
それがまた大変なのである
。乾燥収縮によるパネルの反り返り変形量をチェックしたり、
温度差を計算しそれによる変形をチェックしたり、などなど。
今考えるとたいした事はないが、当時の技術レベルとしてみると相当困難な作業であった。
検討書はページ数が多くなり、わからない説明をしながら、
とりあえず断面は決定したとしよう。そのあとがたいへんなのである。
なにせ自分でも初めてのことなのであまり自信がない。
『本当に大丈夫なんだろうか?』と内心不安であるが、もう後戻りできない。
やがて工事が始まり、徐々にうまくいく気配がしてくると『良かった』と安堵するのだった。
最初のうちはこんな感じである。
この頃から、乾燥収縮による、パネルの反り変形を相殺するために、
いくつかのケースでPC版に逆反りがつけられるようになってきた。
それは計算値より若干少なめの逆反りをあらかじめPCパネルにつけるのである。
これは意外とうまくいったのだ。