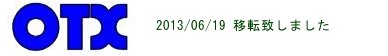
現在は?というと多種多様な要素に対しての検討を必要とし、
それに伴い色々な知識が必要となる。
また、多様な要求に対し柔軟な応用力も必要とされているが、
たとえばコンクリートのひび割れ等に関して考えていくと、
材料学的な知識も必要になってくる。
またFEM解析なども利用することが必要とされてきているため、
その知識、分析能力なども要求されるようになった。
描く施工図の種類としては昔と大きな差はないが、
多様化している現在では、やはりそれなりに描く図面の枚数は増えてきた。
なかでも雨仕舞関係の図面はかなり多くなっている。
ましてや止水が等圧機構等となると一気に図面枚数が増えるものである。
排水経路図とか空気導入口など昔では考えられなかったものだ。
しかし、やがてこれも工法が確立し一般的になれば変わって来るのであろうか。
いや、どうなるかわからない。
そういえば昭和50年代に描いていたPCの挙動図は現在ではほとんど描かれなくなった、
という消え行く図面もあるのだ。
現在は、図面を書きながら考えなくてはならないことが多い。
と、言うよりも図面を描く前に十分考え、それなりに検討し、
の方が正しいかもしれない。
たとえば、
層間変位によって目地幅の計算をする。
ファスナーのスライド量の計算をする。
コンクリートの乾燥収縮による反り変形量の計算をする。
PC打ち込み本石の剛性から応力の計算をする。
ガスケットの漏気量から等圧の計算をする。
場合によっては、鉄骨梁のねじれに関しての計算をする。
などなど。
これらのことは昔ではあまり良く考えられなかった事柄である。
一体いつ頃からこのようになったのであろうか?
しかし、一気に替わったはずは無いので、
それを特記することは少々むづかしいのであるが、
とりあえず、その年表を私の超主観で下記のようにまとめてみた。
昭和13年
不明
昭和27年
この頃は設計事務所、あるいはゼネコン主導型で行われていたと考えられる。
よって、PCメーカーは指示どおりに作っていただけなのであろう。
昭和42年
PCメーカーは設計能力をつけてきた時期。
しかし大きなプロジェクトはゼネコン主導型で行われていたのである。
そのようなプロジェクトに参加したことで、PCメーカーは着実に力をつけていったのである。
昭和50年
どのPCメーカーも力をつけており、設計方法もそこそこ確立されてきた時期。
層間変位に対する認識も行き渡り層間変位図など描かれるようになったのもこの頃である。
しかし、その設計方法に大きな変化がおきた。
昭和51年の鹿島建設のPC標準化の設定であり、それは今までの流れを変えてしまうものであった。
その思想は今でも生きている。
昭和57年
この頃になると、要求も多様化し、いままでより高度な技術を必要とするようになった。
技術的な検討に材料力学的な知識が要求されるようになったのも、この時期からである。
平成6年
現在…