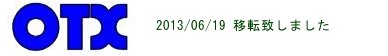
-----昔のマニュアル-----
○ 雨仕舞
この表現からすると、昭和42年頃、もしくはそれ以前より、
二段階シールの原理
the principle of two stage seal
rain barrier open joint
外部に通じた空気層
wind barrier
手探り状態で始めた設計法は約5年後の昭和47年には、
ほぼ確立していたのであろう。
PCCA発足の約2年前であることから考えても、妥当なところだ。
しかし、地震力の扱いに関しては、いまひとつ曖昧だった。
その地震力の扱いが現在のレベルになった時期に関しては、
あまり良く覚えていないが、おそらく昭和53年6月13日に起きた
宮城沖地震の後だったような気がするのである。
この地震で初めて
「地震によるPCcwの脱落事故」
が起り、新聞にも写真が載った。
しかし、その頃のプロジェクトはそれぞれ単独に仕様を決める傾向にあったため、
建物によってはすでに大きな地震力を扱っていたものもあったと考えられる。
しかし、全体の意識として、地震力を現在のように考えるようになったのは、
やはり昭和53年以降であろう。
話は前後するが、昭和51年に私はまず最初に在籍していた会社を退職した。
そして、別のPC会社に入社した。
驚いたことに、そこの商品(PC)の比重は1.1と非常に軽いものであった。
当時は現在のように、PC業界の中での技術的交流がなかったので、
他の会社のPCに対する技術がどの程度のものか全く知らなかったのである。
もっとも、それがゼロだったのではなく、
大きなプロジェクトを数社で担当するような時、
他社の担当者と仲良くなりいろいろな様子を聞く、
と言うようなことはあったけれども「井の中の蛙大河を知らず」である。
そこの会社に入ってすぐに、技術マニュアルを作った記憶がある。
どんな内容だったかはここでは控えるが、
地震力に関しては、とうてい現在のレベルには達していなかった。
そこで念願だった実験を行うことが出来たのである。
当時年間?万円の予算を個人的に確保できたのは珍しいケースだったと思う。
当時その会社では、地方向けに代理店を使いPCcwの販売をしていたのだった。
そこで、私は既製品の企画を出したのであるが、
金利負担を考えると難しいと言うようなことでその企画は没になったが、
そのとき考えた企画ファスナーだけは案が通った。
もともと私は機械工学が好きで最初はそちらをやっていたこともあり、
斑状黒煙鋳鉄(ダクタイル)を使ったのである。
早速、実験計画をが始まった。
確か、昭和52年のことだったと思う。
鋳鉄メーカーには、おいしい話をして作ってもらった記憶がある。
最初の実験は見事に失敗。コンクリートの剛性を
過大評価しすぎてしまったことが原因だった。
すぐに改良案を作り、第二回目は完璧に成功。
早速試験報告書を作成したのである。
荷重―変形曲線のカーブが良かったのを覚えている。
「Fale safe(安全確保)」と言う考え方の重要さを、
報告書を見ていただいた大学の教授から、このとき初めて習ったのであった。
また、この頃、初めて評定用のPCcwの検討書を作成した。
これも昭和52年頃だったと思う。
もっとも、最初から評定用のものを作ったのではなく、
いつも通りに検討書を作成していたのだが、
気が付いたらページ数が非常に多く、見栄えもする、
と言うようなことで、それがそのまま評定用の資料になった。
おかげで、その工事は受注できた。
このとき、初めて技術用サービスの重要性を認識したのである。
今度は設計売り込みで大学の教授のところを訪ねた。
確か、その大学で新校舎建設計画の時期だったと思う。
担当教授の「パラペットの笠木のシールが切れたら?」と言う質問に対し、
「笠置部分に隠し樋を入れましょう」と、
雑誌で読んだ記憶を頼りにそういったのであった。
いざ、本番の施工図のとき、その隠し樋のことは覚えていたのであるが、
適当な材料も思いつかず、黙ってそれを省いてしまった。
さて、建物は完成した。おそらく翌年の夏だったと思う。
大学から電話がかかってきた。「雨が漏る」という内容である。
しまった、ちゃんとやればよかった。後悔先に立たず、である。
理由は、なんと笠木の天端のシールを
からす
が食べたのか、いたずらしたのか、
つついて穴をあけてしまったのだった。
当時のシール材はポリサルファイド系が主流であった。
その後、その大学から追加の仕事が来たかどうかわからない。
また、昭和53年のことだったと思う。
その会社の専務が突然言い出した。
「コンピュータで版図を書こう」
その当時CADのキャの字も無い頃であり、
到底一般的ではなかったと思う。
なのに、電算室の室長に相談し、
ある大手ソフトメーカーと打ち合わせをすることにした。
「こんな図面を書きたいのだが…..」
やがて先方からデモの連絡が来た。
早速見に行く。「う〜ん、本当に描いている」
タイルを一枚づつ書くのに感心したものだった。
もっとも、渡したサンプル図面がそうだった。
A3サイズのプロッターを?ビットのコンピューターで
ドライブするという構成でお値段は?千万円と言う事であった。
デモ用のため座標をパンチカードで用意するもので、
実用的には使えないものであった。
しかし、その後もしばらく打ち合わせを行い、
現実化に向けて試行錯誤したのであるが、
汎用性と入力性の解決策がなかなか見つからなかった。
結局工場にオートクレープの増設するのに資金がいるということで、
その計画は中止となったのであるが、それは時代の先を読んだ良い判断だったと思う。
今となってみると、あの頃実現させたかった。
余談ではあるが、電算質の室長と真剣にコンピューターで
推理小説の構成が出来ないか、いろいろ話し合ったことを思い出す。
結局、そのようなものがPC業界に出てきたのは、
それから約5年後の昭和58年であった。
それは特定仕様の、つまりその工事専用にプログラムを組んだものである。
その2年後の昭和60年には、汎用性を持った
PCF用の連続自動出力プログラムも売り出されたのである。
それは、昼間のうちにデータ―を入力し、夜間に自動出力するというものであった。
今のような、ドラフター代わりのCADの登場は、まだまだこの後の話になる。