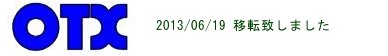
-----昔の知恵比べ-----
当時リブ版が圧倒的に多かった。
それも版部の薄いやつ(80ミリ程度)。
そんな時、やはりリブ版で打ちっぱなしの工事があった。
コンクリートの種類は覚えていないが、
このままではコンクリートの乾燥速度の違いに色むらがでる、
ということで考え抜いたあげく
フラットな断面に変更した。
しかしそんな努力も空しく、結局色むらは出てしまった。
また、その頃はリブ版のクラックが問題になり始めていた。
そこでリブ版で超高層のビルで、開口の上の部分がリブ版タイプになる現場では、
当然クラックを防止すべくバランスよくリブ配置を決めた。自信を持って作ったのである。
しかし、やはり健闘空しくクラックが入ってしまった。
どうやら剛性のバランスが悪かったようだ。
これとは別に、ゴンドラガイドレールのクラックも問題にされていた。
ある工事でもガイドレールがあった。
当然、十分な断面を確保し、施工誤差さえ問題なければ強度的には大丈夫と、
これも自信を持って作ったのだがまたしても失敗。
ヘアークラックが無数に入ってしまったのである。
どうも言い訳になってしまうが、この頃セメントの質が変わったような気がしてならない。
確証は無いが。
こう書くと失敗した話ばかりで
「一体何を工夫したと言うんだ?」
と言われるかもしれない。
今では、
こんな失敗は当然回避できるのだが、
その当時はこのレベルのことが大きな問題であり、
それ以外のことまで考えている余裕が無かったのである。
更に言えば、そのための知識も無かったということだと思う。
それと、うまくいったのはあまり覚えていないだけかもしれない。
そう、残念な思い出がある。
その当時PC版の自重受けは
コンクリートの『アゴ』で支持する方式が一般的であった。
そんな頃、金物アゴを考えた。
早速、図面を描き工事課長に見せたのである。
当時、その会社では取り付け詳細図は工事課長がチェックする、
と言うしきたりだったのだ。
課長曰く
「君、こんなのちょっとぶつけたら取れちゃうじゃないか」
その時は仕方なくあきらめたわけであるが、
今考えると残念だった。
しかし初めてのことなので反論する材料も無いし、
まして実験をさせてもらうなど許されるはずも無い時代だった。
「実験したい」
「そんなことより図面を描け、馬鹿もん!」
こんな時代であるからどのような計算書を作成していたのかは、
はっきり覚えていないのであるが、
ひとつだけ記憶が残っていることがあるので、
ここに参考に記載しよう。
たぶんに、これも失敗したケースだったのだが。
当時、窓パネルの方立てはやたら細かった。
それにもめげず、もっと細い方立てのパネルで、
しかも開口も大きかった版があった。
さすがにまずいと思い、面内剛性の計算を行ったのであった。
すると、方立ての幅を細くすればするほど面内変形に対して有利だったのである。
そんなわけで設計図通りの断面で行ったのであった。
結果がどうなったのか覚えていないが、
どうも計算を間違ったことだけは確かである。
と言うことは、やはり何らかの計算を行い、
それを計算書として提出していた、と考えてよいと思う。
当時の計算根拠は
「日本建築学会の鉄筋コンクリート構造計算基準」
「鋼構造設計基準」
そして資料として
「建築学便覧」等である。
当時の「建築学便覧」は昭和31年の出版のもので
昭和43年に絶版となったものであった。
「鋼構造設計基準」は昭和42年JIS大改革以降のものであり
「鉄筋コンクリート構造計算基準は技術進歩のために
昭和33年代改定されており、さほど現在と違いはない。
そして、私が勤めていたその会社では昭和47年に
社内設計マニュアルを作成していたと言う。
実は私はその存在を知らなかった。
最近になって原稿を書くために調べていたとき
「これがあったよ」
とその資料を頂いたのであった。
それを読んで驚いた。実にしっかりした内容だったのである。
ここで詳細に紹介できないのが残念に思うが、
当時の設計技術はかなりのレベルで確立されていたことを示すものである。
そのマニュアルは当時の設計課長が作成したものであった。
その方は学者タイプで比較的おとなしく、
あまり自己主張をされなかったことを覚えている。
もっと「でたがり」
であったなら
PC業界を引っ張っていくことが出来たのに、と今考えると残念に思う。
実はその方は会社を退職され大学の教授になってしまったのだ。
そういえば、私はそのマニュアルも知らないはずである。
私がその会社を退職した後に出来たものなのだから。
(おかしな話であるが、私はその会社に二度入社し二度退職していたのである。全く何を考えていたのやら)
さて、そのマニュアルの中で面白い記述がある。それを紹介する。